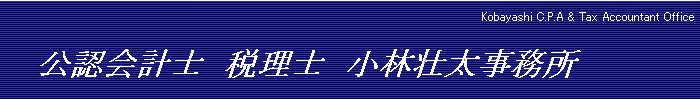
”公益法人制度改革の概要”
ご存知の方も多いかと思いますが、公益法人制度が平成20年12月より変更されました。これに伴い、平成25年11月までに、従来の公益法人は再度認定を受けなければ公益法人としての資格が無くなってしまいます。
公益認定は、内閣府に設置された公益認定等委員会によって審議されて、内閣総理大臣が認定することになります。(都道府県をまたがないもの等は、都道府県レベルで審議、認定されます。)
公益認定の申請は、平成25年11月までの期間であれば何度も申請できますので、多くの公益法人は「とりあえず様子をみて」「1,2年後に申請し」「4,5年後までには認定を受ける」と予定しているようです。ただし、公益認定の申請を予定している法人数は膨大で、申請してから結果が出るまで、かなりの時間がかかると想定されます。再申請の可能性を考えれば、早めの対応が必要となります。
さて、公益認定基準とはどのようなものなのでしょうか。多くの公益法人が心配している状況からも分かるよう、ハードルは低いものではありません。認定の要件は全部で18種類あるのですが、特に問題になりそうなものは次のものになります。
法人の主たる目的
公益法人なので、公益目的(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する)事業を主たる目的とする必要があります。結果的には世間一般の人々の利益に寄与する事業であっても、会費を集めて、会員のみを対象としてセミナーや出版物を発行している法人等は、方針を変える必要があるかもしれま せん。
収支相償
ご存知ない方も多いかと思いますが、公益法人は公益目的事業のみを行っているとは限りません。寄付が多額に集まらない法人などは、収益事業を行い、それを財源として公益事業を行います。ただ、公益法人と謳っている以上は、「公益事業費」=「収益事業よる収益」のバランスが求められます。
公益目的事業費率
収支相償と同じで、法人の全事業費のうち半分は公益目的事業費であることが求められます。
遊休財産額
こちらも収支相償と同じ考え方によるもので、内部留保は翌年に見込まれる公益目的事業費を超えてはいけないという規制になります。公益法人では、公益目的のための寄付を受けることも多く、寄付者の意思通りの支出が求められます。








